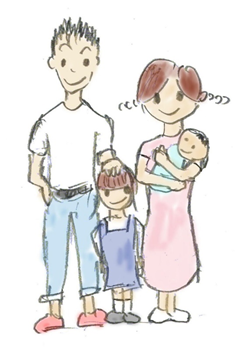心に残った看護 ~看護をつむぐ~
看護をつむぐとは、当院での看護実践の積み重ねが、看護部理念の「おひとりおひとりを大切にした看護」になっていくということを表しました。当院では、毎年心に残る看護実践をナラティブにしています。
当院のナラティブをご紹介します。
ナラティブとは「物語」という意味です。私たちが日々経験する看護場面は1つとして同じものはありません。その時に流れる空気、時間、心の動きは一瞬一瞬変化し、物語となって綴られていきます。ここに描かれたナラティブを読むと、当院看護部の「おひとりおひとりを大切にした看護」が見えてきます。
このページが、当院の看護を知っていただく場になることを願っています。
令和7年
握りしめた手
脳梗塞を発症したAさんは、癌の手術をした時と同じ病棟に、再び入院をすることになりました。前回の入院は、術後の痛みで離床が進まず、リハビリ病院への転院を経て自宅退院となった方でした。入院で担当となった私に、「あなたを覚えているよ。前は黄緑色(2年目の看護師が着用)のストラップをつけていたよね」と声を掛けて下さり、とても嬉しかったことを記憶しています。
今回、Aさんは薬物治療によって入院時にあった麻痺がなくなり、スタスタと歩けるようになり、私は前回の入院時とは違ったAさんの姿に感動しました。その時は、このまま自宅に帰れるだろうと思っていましたが、入院中に癌の転移が見つかり徐々に体力が落ちていって、だんだんと起き上がれなくなりました。そんなある日、医師からAさんに病状説明がありました。医師は病状の変化を説明する際に、今後は病気と付き合っていくことになるが、Aさんはこれまで、癌や手術などを経験しながらも、自宅退院できるほど治療に対して向き合っていると労い、「今回も自宅に帰れるように頑張りましょう」と声をかけていました。Aさんはそれを聞いて「励まされました。また家に戻るためには頑張らないとね。先生ありがとうございます」と仰っていました。同席した私は、Aさんと医師には強い信頼関係があるのだと感じました。しかし、その後のAさんは体力がどんどん落ちていることを自覚し、「家には帰りたいという気持ちはあるけど、身体が付いていかないのが悲しい」とつぶやくようになりました。そして、自宅退院は難しくなり、リハビリ病院を探すことになりました。
嘔吐が続くようになり、短い距離の歩行でも息切れがして、できないことが増えていく度にAさんは「こんなこともできなくなって、迷惑を掛けてごめんね」と看護師を気遣う言葉がけが多くなりました。一番つらいのは、Aさんであるはずなのにと申し訳ない気持ちで一杯になりました。私がAさんに何かできることはないかと考えた結果、リハビリ中に歩いている様子を見かけたら「今日は歩いているのを見ましたよ。体調どうですか?」と訪室して声をかけたり、プラスの言葉がけをするように意識して関わりました。また、アイス枕で頭を冷やすと頭痛が紛れると仰っていたので、Aさんから依頼される前に声をかけたりすることで、無用な気遣いをさせずに入院生活を送っていただけるように努めました。「よく気づいたね、ありがとう」と温かい言葉を掛けてくださり、「今日はご飯、いつもより食べられたよ」と前向きな発言もみられました。私は日々の関わりの中で、Aさんと信頼関係が築けたように感じました。
Aさんが転院するまで話しやすい環境をもっと作っていこうと思っていた矢先の、ある日のことでした。Aさんに再び麻痺が出現してしまいました。そして、その数日後に病状が急激に悪化してしまいました。「これ以上頑張れない、迷惑かけたくない」とAさんは言っていたようです。マイナスな発言が多くなったAさんの心情を慮ると、私自身もとても悲しい気持ちになりましたが、看護師として私ができることを精一杯していこうと思いました。Aさんを担当した時にシャワー浴の提案をしたところ、「入りたい」と応えてくださいました。入浴の時間を設けて、身体にゆっくりお湯をかけると「気持ち良いね、一時的だけど辛いのも忘れられるわ」と喜んでくださいました。私は、Aさんの苦痛を少しでも緩和することができて良かったと強く思いました。
しかし、その数日後に私が夜勤でAさんを担当する時には、高い濃度の酸素が投与されていました。目はうつろでしたが、「今日はあなたなのね。よろしくね。朝ご飯は食べたいな」と仰いました。誤嚥のリスクがあったため先輩看護師に相談したところ、朝の状態をみて、できるだけ希望に添えるようにしようということになりました。早朝、Aさんは咳嗽が多くなり呼吸もしづらそうでした。不安のためなのかナースコールの回数が多くなりました。訪室する度に私はAさんの手を握って、「また来ますから呼んで下さいね」と声をかけました。朝食の時間になると、Aさんはほとんど咳もなく落ち着いていたので食事の準備をしました。Aさんは、ご家族が準備してくださったブドウを、時間をかけて召し上がり「おいしい。食べれて良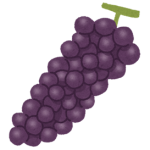 かった」とにっこりされました。Aさんは、緩和ケア病棟への移動を希望していたため、私が関わることができるのは、もしかしたら、この夜勤が最後になってしまうのではないだろうかと思い、退勤前に訪室しました。訪室したものの、なんと声をかけたら良いのか分からず、手を握りながら不覚にも涙をこぼしてしまいました。私が「夜はありがとうございました。私はこれで勤務が終わるので...」と言うと、「だめ、ずっとここにいて」と手を強く握り返し、離そうとしてくれませんでした。いつも看護師に気を遣ってばかりのAさんだったので、思いもよらぬ行動に驚きましたが、その分、Aさんの不安が強く感じられました。そして、Aさんが手を握り返してくださった行動は、Aさんとの信頼関係ができていたからこそだと思いました。数日後に出勤すると、Aさんは私が夜勤明けのあの日に緩和ケア病棟に移動されており、その後、鎮静剤が開始になったと聞きました。
かった」とにっこりされました。Aさんは、緩和ケア病棟への移動を希望していたため、私が関わることができるのは、もしかしたら、この夜勤が最後になってしまうのではないだろうかと思い、退勤前に訪室しました。訪室したものの、なんと声をかけたら良いのか分からず、手を握りながら不覚にも涙をこぼしてしまいました。私が「夜はありがとうございました。私はこれで勤務が終わるので...」と言うと、「だめ、ずっとここにいて」と手を強く握り返し、離そうとしてくれませんでした。いつも看護師に気を遣ってばかりのAさんだったので、思いもよらぬ行動に驚きましたが、その分、Aさんの不安が強く感じられました。そして、Aさんが手を握り返してくださった行動は、Aさんとの信頼関係ができていたからこそだと思いました。数日後に出勤すると、Aさんは私が夜勤明けのあの日に緩和ケア病棟に移動されており、その後、鎮静剤が開始になったと聞きました。
今回、私は、Aさんの性格や生活スタイルを知り、Aさんと関わる中で、私の行動は、Aさんのニーズを満たしていることをAさんの言動や表情から感じました。患者さんのニーズはその都度変わっていくので、日頃の観察力やコミュニケーションも大事にし、その人その人にとっての最善の看護をこれからも実践しつづけたいと思います。
患者と一緒に取り戻した日常
 脳疾患治療のために入院されたAさんは、同時にコロナにも罹患しており、隔離を余儀なくされていました。入院前までのAさんは退職した後も、町内会で活発な活動をされていましたが、入院後の隔離生活が続くことによってADLは徐々に低下していき、転倒したことを機にセンサーを使った見守りが必要な状態になりました。周りの人に気を遣うAさんは、看護師に気兼ねをしていたのか、徐々にベッドから離れることをしなくなり、立位保持も難しくなっていきました。離床の機会が減ってくると食事の量も減っていき、毎食に小さいカップ麺を食べるだけになってしまいました。そして、低栄養の影響で徐々に体が浮腫んでしまい、ついにADLはベッド上になりました。
脳疾患治療のために入院されたAさんは、同時にコロナにも罹患しており、隔離を余儀なくされていました。入院前までのAさんは退職した後も、町内会で活発な活動をされていましたが、入院後の隔離生活が続くことによってADLは徐々に低下していき、転倒したことを機にセンサーを使った見守りが必要な状態になりました。周りの人に気を遣うAさんは、看護師に気兼ねをしていたのか、徐々にベッドから離れることをしなくなり、立位保持も難しくなっていきました。離床の機会が減ってくると食事の量も減っていき、毎食に小さいカップ麺を食べるだけになってしまいました。そして、低栄養の影響で徐々に体が浮腫んでしまい、ついにADLはベッド上になりました。
点滴や内服でコロナの治療はしていたものの、免疫力の低さから陽性の状態が続きました。Aさんは自分の気持ちを自ら話さない方でしたが、陽性が続くことでどこか気力がなくなっているようにみえました。こちらからベッド上でできる運動や食事を促しても断ることが多くなっていました。また、隔離期間が長くなり、家族とも面会することができず、病院や医師、看護師に対して納得がいかない様子がみられるようになりました。妻とは携帯電話で連絡は取っていたようですが、口腔機能の衰えから滑舌が悪くなり、電話でのコミュニケーションは難しくなっていました。私は妻が来棟した時に最近の様子をお伝えすると、妻は「電話をしても何を話しているかわからず、会話ができないことがあり不安です」、「病院でどのように過ごしているのか知りたい」と仰いました。私はリーダーナースに相談した上で、Aさんに「携帯電話やモニター越しのビデオ通話で奥さんと話しませんか」と提案してみましたが、ビデオ通話は嫌だと断られました。入院前よりやつれている姿を見せたくなかったようでした。
そこで、私はAさんに「Aさんの顔は映さず、奥さんの顔だけが見られるようにします。奧さんはAさんの顔を一目でもいいからみたいと仰っています」とお伝えしました。するとAさんは、「自分の顔を見せなくても良いのなら」とモニター越しの面会を承諾してくださいました。Aさんの言葉数は少なかったですが、妻の顔を見ることができて安心されたようでした。滑舌が悪くなっていたため、私が言葉を補いながらの面会でしたが、Aさんは久しぶりに妻と会話ができて、お互い嬉しそうでした。
妻がAさんのお顔をみたいご様子であったので、最後にもう一度Aさんに、「Aさんのお顔を映してもいいですか」と尋ねてみると、「良いよ」、と言ってくださいました。妻はAさんの顔を見て驚いた様子はあったものの、「変わらない笑顔が見られてよかった」と言ってくださいました。Aさんは面会後に少しずつ気力が沸いてきたのか、私が「浮腫みの改善のためにベッド上で足を動かしませんか」と提案すると受け入れてくれました。私は、「少しずつ動けるようにして、食事も少しずつで良いので食べる量を増やして筋力をつけて、自宅へ帰られるように一緒に頑張りましょう」とお伝えしました。その日から、私はAさんを受け持った際には体調を見ながら運動を促したり、洗面所へ歩いていただくようにしたりと離床を進めていきました。Aさんは洗面所へ行った際、「久しぶりに外の景色を見たな、綺麗だな、ありがとう」と嬉しそうに言ってくださいました。そして、いそいそと歯磨きをして髭を剃り、顔にローションを塗っていました。いつもより背筋が伸びて生き生きとしているように見えました。

 Aさんに時間をかけて関わっていく中で気がついたことがあります。洗面所にお誘いし、ご自身のお顔を鏡で見ることでAさんは髭剃りや身なりを整えようという意識を取り戻すようになったことです。離床は身体機能の廃用が防げることや気分転換になります。
Aさんに時間をかけて関わっていく中で気がついたことがあります。洗面所にお誘いし、ご自身のお顔を鏡で見ることでAさんは髭剃りや身なりを整えようという意識を取り戻すようになったことです。離床は身体機能の廃用が防げることや気分転換になります。
あれから私は、訪室時にはすぐにAさんを洗面所へ誘導し、自分でできる整容をしてもらっている間に下膳や部屋の掃除、ベッドメーキングをして、退室する前に一緒にベッドへ戻るようにしました。そして午後の検温時や点滴交換時などの訪室の際には「筋トレしましょ~!」と声かけをしました。最初は、ベッドの上で足首を動かすだけでしたが、退院が近づく頃にはスクワットができるようになっていました。声かけをしないと動かなかったAさんでしたが、離床が進むとともに認知機能も回復し、理学療法士に教えてもらったリハビリを自ら行うようになりました。食事も摂れるようになりコロナも陰性化して、歩いて退院されました。一時は隔離されたまま亡くなることが危惧されたほどの状態だったので、とても嬉しくやりがいを感じました。
看護は決められた業務に加えて、患者さんの状態など様々な要因でスケジュールが常に変更され、時間に追われながら多重業務を遂行するため、頭も体力も使う仕事だと思っています。歯磨きや髭剃りはベッド上でも行える行為ですし、洗面所への移動がない分、時間の短縮にはなります。実際のところ、看護師のペースで早くケアを実施して仕事を進めたくなる時は沢山あります。しかし、「今」時間と手間がかかることでも、それが患者さんの回復につながれば、早期離床が実現し、元の生活を早く取り戻せると思います。自分の未熟さや日常の忙しさから視野が狭くなっていき自分の業務を優先してしまいがちですが、こころにゆとりを持って目の前にはどのような援助や声かけが必要なのか冷静に考えて行動していきたいです。
急性期病院に入院するということは、患者さんとその家族にとって身体的にも精神的にもストレスがかかることだと思います。そこで働く看護師として、患者さんの人生の中で辛い時期に傍にいて、その辛さを和らげ少しでも穏やかに過ごせるよう、また辛い時間が少しでも短くなるようにこれからも支援していきたいと思います
看護をつなぐ
 Aさんは食道癌で化学放射線療法を行っていました。しかし、その途中の検査で肺炎像が認められたため治療は中止となりました。その原因を探るため内視鏡検査をすることになり、私はその時に検査担当として初めてAさんにお会いしました。Aさんはとても痩せていて、車椅子から検査用ベッドへ移動するのもやっとという様子でした。「検査を担当させていただきます○○です、よろしくお願いします」と挨拶すると、「お願いします」と返事をしてくださいましたが、表情は引きつっていて不安な気持ちと緊張していることが伝わってきました。
Aさんは食道癌で化学放射線療法を行っていました。しかし、その途中の検査で肺炎像が認められたため治療は中止となりました。その原因を探るため内視鏡検査をすることになり、私はその時に検査担当として初めてAさんにお会いしました。Aさんはとても痩せていて、車椅子から検査用ベッドへ移動するのもやっとという様子でした。「検査を担当させていただきます○○です、よろしくお願いします」と挨拶すると、「お願いします」と返事をしてくださいましたが、表情は引きつっていて不安な気持ちと緊張していることが伝わってきました。
内視鏡検査は、息苦しさや腹部の張りで苦痛を感じる方が多くいらっしゃいます。そのため私は、検査中はAさんを励ましながら背中をさすり、唾液を誤嚥しないように口腔内をこまめに吸引することで、安全かつ少しでも苦痛を少なく検査を受けていただけるようにしました。造影剤を注入すると激しくむせ込み、身体は仰臥位、顔だけ左を向くという苦しい検査体位でAさんはとてもつらそうな顔をしていました。私は、検査が1秒でも早く終わることを祈りながら「もう少しだから頑張りましょうね」と励ましながら介助しました。検査の結果、腫瘍自体は治療の効果で小さくなっていましたが、合併症の併発による誤嚥性肺炎と診断されました。
検査が終わって真っ先に「お疲れ様でした、大変でしたね」と労いの言葉をかけました。Aさんは口元をティッシュで拭いながら「ありがとうございました」と疲労感を浮かべながらも検査が終わって少しホッとしたような表情で静かに答えてくださいました。検査用ベッドの端に座ったところで主治医から「腫瘍は小さくなっているけど、食道に穴が空いているから治療は中止です。ご飯も水分もだめだよ。穴を塞ぐ治療は呼吸器内科の先生と相談するからね」と告げられました。その時のAさんは、うなずきながら医師の説明を聞いていましたが、時折一点を見つめて言葉を失っているようで、その小さな身体からは大きな不安と絶望感が感じられ、状況を受け止められていない様子でした。主治医がAさんに「今日の5時、奥さんは病院に来られる?」と尋ねると、「え?今日?」「今日は難しいかな…。えっと、明日は?えっと…」と戸惑っていました。そんなAさんの返事を待つことなく、医師は次の検査のため足早に検査室を出て行かれました。
私は、Aさんの思いを聞き、それを受け止めどのような看護が必要となるのか、じっくり関わって一緒に考えたい思いでした。しかし、ここは検査室で他にも検査を受けるために待っている患者さんが大勢おられるのでAさんは退室しなくてはなりません。今、私ができることは病棟看護師に状況を引き継ぎ、Aさんの気持ちや理解度・受容の程度を確認しながら適切な時期に適切なサポートをすることだと考えました。私は改めて、「検査お疲れ様でした、大変でしたね。急なことでショックですよね」と背中をさすりながら声をかけました。「奥様のご都合もあるし先生の予定もあるので、もし今日が難しかったら奥様が病院に来られる日にちと時間を聞いていただいて、3つくらい候補を出しましょうか。分かったら病棟の看護師に伝えてもらえば調整してもらえるので、奥様と一緒にきちんとお話が聞けるようにしましょうね」と日程調整ができるように具体的に提案しました。「あ、そうですか、分かりました」とうつむいていた顔を上げた時は、少しだけ前を向いてもらえた気がしました。迎えに来た病棟看護師に合併症が生じていること、絶飲食となること、検査後に簡単な説明がされたがとてもショックを受けている様子であること、病状説明の調整をお願いしたいことをAさんの前で申し送りました。そして、Aさんに「お疲れ様でした、検査、疲れたと思うのでゆっくり休んでくださいね」と言って見送りました。車椅子で退室するAさんの背中はとても小さく孤独感が感じられました。
私は、自分が考えて行動したことは正しかったのか、もっと寄り添った関わりが必要だったのではないか、自分ではなくもっと経験のあるスタッフが関わっていたらもっと良い関わりができたのではないか…ともやもやしていました。翌日Aさんのカルテを見ると、きちんと病状説明の場が設けられ、奥様と一緒に説明を聞くことができたこと、自分の状況を受け止めて今後どのように過ごしたいか、思いを表出することができたことを知り、少しホッとしました。
 外来看護師となり半年、経験が浅く自分は患者さんのために何ができるのか日々模索しています。何もできない自分に嫌気がさし、悔しさから涙することもたくさんあります。自分が汲み取った対象のニーズは、自分が主体的に介入したいと考えることも多くありましたが、この事例を通して「看護をつなぐ」ということがとても大切だということを学ぶことができました。自分が関わった時点で全てを解決しなくてもいい。限られた時間の中で患者さんに寄り添い、感情を受け止め、患者さんの理解度や受容の程度、状況に合わせた支援ができるよう病棟看護師や他部門に情報をつなぐことができれば、最終的に患者さんの意思決定につなげることができるかもしれない。
外来看護師となり半年、経験が浅く自分は患者さんのために何ができるのか日々模索しています。何もできない自分に嫌気がさし、悔しさから涙することもたくさんあります。自分が汲み取った対象のニーズは、自分が主体的に介入したいと考えることも多くありましたが、この事例を通して「看護をつなぐ」ということがとても大切だということを学ぶことができました。自分が関わった時点で全てを解決しなくてもいい。限られた時間の中で患者さんに寄り添い、感情を受け止め、患者さんの理解度や受容の程度、状況に合わせた支援ができるよう病棟看護師や他部門に情報をつなぐことができれば、最終的に患者さんの意思決定につなげることができるかもしれない。
今回、ご家族を含めてきちんと病状の説明をすることが必要だと病棟看護師に引き継ぐことで、外来看護師に必要であるパイプ役としての役割を果たすことができたと感じました。そして、のちの倫理カンファレンスで、自分の関わりを評価していただけたことはほんの少しだけ自信につながったような気がしています。患者さんが安全・安楽に検査を受けることができるよう、そして看護をつなぐことができるよう、益々努力していきたいと思えた事例でした。
病窓の花
7月のある日、昼休みに妻から「今日は花火大会があるよ」とスマートフォンにメールがあった。妻は4歳になる娘を連れて、夕方から見に行くという。私は夜までの勤務である。娘の浴衣姿や屋台のイカ焼きやビールの味を想像して、少し寂しい気分になりながらも、食事を済ませて仕事に戻った。午後には集中治療室から移動される患者さんがいる。今日も忙しくなりそうだ。
手術目的で入院されていた70歳代のAさんは再手術を経て、当初の予定よりも長く入院することになり、心身共に疲弊しているのが見てとれた。集中治療室からの移動後も、薬剤での心臓の補助が必要で、リハビリで歩行するとすぐに不整脈が出現し、持続的な酸素投与が必要な状態であった。そのような中でも、Aさんは看護師から調子を聞かれると「少しの痛みくらいで他は大丈夫」「本当に良くしていただいて、ありがとうね」と穏やかに笑顔を見せた。Aさんは苦しさや不安などを表情に現さない人という印象だった。
日中の業務も落ち着き、入院患者さんの夕食が運ばれてくる時間になった。私は受け持ち患者さんの配膳を済ませて、記録のため窓側のパソコンへ向かった時だった。「どーん!」という音が聞こえ、窓外を見ると、少し遠くの夜空に花火が上がっていた。私は、諦めていた花火を思いがけず見ることができて、少しだけ気分が晴れた気がした。
 検温でBさんの病室を訪れた時に、「窓から花火が見えるよ」と伝えて、カーテンを開けてみた。するとBさんは思いのほか喜ばれ、晴れやかな笑顔を見せてくれた。私は、Aさんにも知らせようと考えた。その時の私は、Aさんの落ち込んだ気持ちを慰めようとか、特に理由があったわけではない。Bさんに喜んで頂けたことが嬉しくて、Aさんにも花火を見てもらおうと思っただけだった。
検温でBさんの病室を訪れた時に、「窓から花火が見えるよ」と伝えて、カーテンを開けてみた。するとBさんは思いのほか喜ばれ、晴れやかな笑顔を見せてくれた。私は、Aさんにも知らせようと考えた。その時の私は、Aさんの落ち込んだ気持ちを慰めようとか、特に理由があったわけではない。Bさんに喜んで頂けたことが嬉しくて、Aさんにも花火を見てもらおうと思っただけだった。
食事を終えてベッド上でのんびり過ごされていたAさんは、窓とは逆のテレビの方を向いていた。花火が見えることを伝えると、「あら!ほんと?見たいわね」と身体を窓の方へ向けようとされたが、傷の痛みで上手く動けない様子であった。病室には他に患者さんは居らず、入室予定もなかったため、私はAさんのベッドを花火の見やすい位置まで移動させた。「わあ~!ほんとに見えたわ!」とその瞬間、Aさんの表情が明るくなったのがわかった。「病院で花火が見られるなんて思わなかった。見やすいように色々考えてくれたのね」と、Aさんは嬉しそうに仰った。「小さくて申し訳ありません」と伝えると、「ううん、とてもキレイ…今年はもう見られないと思っていました。病気は沢山してきたし、手術は出血も多くて、輸血もいっぱいしたって聞きましたから」と。受け持っていた他の患者さんが食後で休まれていたこともあり、私は椅子に座りAさんのお話しを聴くことにした。「こんなになってしまって、これからどうなるだろうって、考えちゃうことが止まらないときもあってね」と仰った。Aさんからこのような言葉が聞いたのは、その日が初めてのことだった。私がAさんにも花火を見てもらおうと考えたのは、少しでも気晴らしになればなと思ったぐらいだったが、Aさんにとって病室から見た花火は、不安やストレスのかかる入院生活の中で、私が想像する以上に心が動くエピソードとなったようだった。
こんなにもAさんに喜んでいただいけた要因には、その日に偶然に上がっていた花火がよく見えるようにベッドを動かして調整した私の行動も含まれていたと信じている。日々のケアや接し方の中には、特別なことでなくても患者さんの入院生活の不安やストレスを和らげる医療者の行為がある。例えば、ただペットボトルの蓋を開けるだけの行為でも、思った以上に喜ばれた経験がある。患者のために行った何気ないケアであっても、その積み重ねが信頼関係を築き、患者が「この病院で良かった」と感じられることに繋がるのではないかと思う。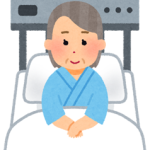
後日、Aさんがとても喜んでいたことを他の看護師から聞き、ご挨拶に伺った。Aさんは、和やかな笑顔で迎えてくださり「あの花火は今までで見た中で、一番の花火だった。ほんとうに嬉しかった」と仰った。あの時以来、私は病室から花火を見ることはなかったが、Aさんと見た花火は忘れることはないだろう。
聞き取れなかったかすかな声
Aさんは術後の合併症のため入院された70代の女性である。循環動態が不安定で24時間の持続透析を行っていた。仙骨部には大きな褥瘡があり、体位変換や褥瘡処置のたびに「いたーい!」と叫んでいた。疼痛に対して緩和ケアチームが介入して改善し、処置の度に叫ぶことはなくなった。しかし、鎮痛剤によって呼吸が抑制されてしまい補助呼吸器の装着が必要となった。この出来事は入院して10日ほど経過した日のことだった。
 22時頃に体位変換した後、Aさんは腰をよじるように動かしていた。このわずかな労作でも呼吸は浅く速くなっていた。私はAさんと相談しながら体位を調整した。今度は口渇感を訴えたので、氷水で湿らせたスポンジブラシで保湿した。それでもAさんは荒い呼吸のままで不安気な表情だった。私はAさんに「眠れそうですか?」と尋ねると、Aさんは「寝ると、逝っちゃう」とぼそっと言い、ナースコールを強く握りしめていた。そのようなAさんを見て、死を予期し恐怖心を抱いていて、ナースコールはAさんにとって頼みの綱なのだろうと感じた。私はAさんに「大丈夫、そばにいますからね」と伝え、ベッドサイドにいるようにした。Aさんは「胸や腰も全部痛い」と言い、私はその都度、腰や背中をさすった。Aさんは「ありがとう」と言ってくれた。ただ、Aさんの「全部痛い」という言葉が私の心に引っかかっていた。Aさんのそばにいながら、全部痛いとはどういう意味かと考えた。それは傷や褥瘡の疼痛、長期臥床に伴う肩や腰の疼痛のような身体的な苦痛だけでなく、心理的な痛み、スピリチュアルペインも抱いているのだろうと感じた。そして「寝ると、逝っちゃう」という発言はその現れだと考えた。Aさんの様々な苦痛を少しでも軽減したいと思い、Aさんの肩や腰をさすったり、手を握ったりしながら30分ほどベッドサイドで過ごした。
22時頃に体位変換した後、Aさんは腰をよじるように動かしていた。このわずかな労作でも呼吸は浅く速くなっていた。私はAさんと相談しながら体位を調整した。今度は口渇感を訴えたので、氷水で湿らせたスポンジブラシで保湿した。それでもAさんは荒い呼吸のままで不安気な表情だった。私はAさんに「眠れそうですか?」と尋ねると、Aさんは「寝ると、逝っちゃう」とぼそっと言い、ナースコールを強く握りしめていた。そのようなAさんを見て、死を予期し恐怖心を抱いていて、ナースコールはAさんにとって頼みの綱なのだろうと感じた。私はAさんに「大丈夫、そばにいますからね」と伝え、ベッドサイドにいるようにした。Aさんは「胸や腰も全部痛い」と言い、私はその都度、腰や背中をさすった。Aさんは「ありがとう」と言ってくれた。ただ、Aさんの「全部痛い」という言葉が私の心に引っかかっていた。Aさんのそばにいながら、全部痛いとはどういう意味かと考えた。それは傷や褥瘡の疼痛、長期臥床に伴う肩や腰の疼痛のような身体的な苦痛だけでなく、心理的な痛み、スピリチュアルペインも抱いているのだろうと感じた。そして「寝ると、逝っちゃう」という発言はその現れだと考えた。Aさんの様々な苦痛を少しでも軽減したいと思い、Aさんの肩や腰をさすったり、手を握ったりしながら30分ほどベッドサイドで過ごした。
Aさんは0時頃から入眠し始め呼吸数も落ち着いてきた。体位変換の時にAさんは時々目をゆっくり開けた。私はAさんと視線が合ったが、どのように声をかけたらいいのか分からなかったので、「私はここにいますよ」という気持ちでゆっくり頷くと、Aさんも私を見て頷いてくれた。朝になってAさんに「眠れましたか?」と尋ねると、Aさんはゆっくり頷いた。ナースコールを握る手も少し緩んでいた。私は自分がそばにいて少しでも安心できたかなと思った。朝の治療薬を投与するとき、Aさんに「薬を流しますね」と声をかけた。すると、Aさんは何度も首を横に振った。「もう薬は流して欲しくないということですか?」とそっと尋ねると、Aさんはゆっくり頷いた。
Aさんは約10日にわたる治療に疲弊していて、もう治療をやめたいのだろうと感じた。その上で、Aさんはこの先何を希望されるのだろうかと思いを巡らせた。私はAさんに「『もし治療をやめて好きなことをしても良いよ』と言われたら何がしたいですか?」と聞いた。Aさんは答えてくださったが、昨晩よりも声がか細くて周辺器機の音にかき消されてしまい、はっきり聞き取れたのは「家」と「家族」という言葉だけだった。私は推測して「家に帰って家族と過ごしたいですか?」と聞くとAさんは頷いた。「帰りたいですよね。医師に伝えておきますからね」と声をかけてから薬剤を投与した。その時Aさんは悲しげな表情だった。
私は昨晩の「寝ると、逝っちゃう」という発言や薬剤投与を拒否した際の会話をきっかけに、治療方針を見直す必要があると考えた。Aさんの身体的苦痛、心理的・社会的な苦痛、スピリチュアルペインがここまで露わとなった今、このまま治療を継続するのはAさんにとってプラスになるのだろうか。Aさんの苦痛を緩和する方針に切り替えた方がAさんの希望に添うことができるのではないかと考えた。
また、昨晩と今朝では明らかに声に力がなくなっており、Aさんの体力や気力はもう限界で残された時間は長くないと察した。私はこれらを記録に残してこの日の勤務を終えた。その後、主治医と家族で話し合われ苦痛を緩和する方針となった。数日後、Aさんは他の病棟に移動してお亡くなりになった。
私が関われたあの日は、私自身もしんどいなと思った。なぜならば、Aさんの抱える苦痛を思うと自分も胸が苦しくなる一方で、どのように関わればよいか、どのように声かけすればよいか分からない中で過ごしたからだ。しかし、後から振り返ってみると、夜はAさんの「寝ると、逝っちゃう」という発言をスピリチュアルペインだとアセスメントして、そばに寄り添って不安や苦痛を軽減できるように関わることができたと思う。朝になってAさんのナースコールを握る手が緩くなったのは、Aさんが少しでも安心して入眠できたのではないかと捉えたい。ただ、翌朝の私の問いかけに、必死に答えてくださったAさんの言葉を一部しか聞き取れなかったことが残念でたまらない。Aさんの表情やかすかな声から、体力も気力も限界の中で、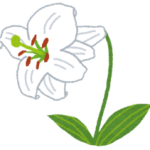 精一杯の力を振り絞って答えてくれたのだろうと思うと、「もう一度、お願いします」とは聞き直せなかった。もし、あの時Aさんが話されたことを全て聞き取れていたら会話の内容も変わっていただろうし、より正確にAさんの希望を知って行動で きたのかもしれない、と悔いが残る。今回は、聞き取れた「家」や「家族」から推測して、Aさんの思いを確認できた。それを記録に残すことで、最終的にはAさんの苦痛を緩和する方針に繋がった。私は、この体験からの学びを大切にして、これからは患者さんの発するかすかな声や小さな変化もとりこぼさないように努めたいと思った。
精一杯の力を振り絞って答えてくれたのだろうと思うと、「もう一度、お願いします」とは聞き直せなかった。もし、あの時Aさんが話されたことを全て聞き取れていたら会話の内容も変わっていただろうし、より正確にAさんの希望を知って行動で きたのかもしれない、と悔いが残る。今回は、聞き取れた「家」や「家族」から推測して、Aさんの思いを確認できた。それを記録に残すことで、最終的にはAさんの苦痛を緩和する方針に繋がった。私は、この体験からの学びを大切にして、これからは患者さんの発するかすかな声や小さな変化もとりこぼさないように努めたいと思った。
令和 6 年
令和5年
令和4年